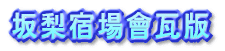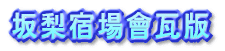|
さかなし宿場會 瓦版
拾弐月第七拾八号 平成拾七年十弐月四日(日)
一、宿場會はゆっくりでも留まることなく常に前へ歩き続ける事
拾壱月例会報 十壱月十参日(日)十九名
会長挨拶の後、田園空間博物館(田空)からのお客様を田空事務局佐藤さんが紹介した。
お客さまは、各々自己紹介をした。
順にサテライト部、副部長阿部さん、同部藏原さん、石本さん、篠田さん、種野さん
少し遅れて初めてのギャラリー参加者を代表して橋口さん。
以上七名の方々がを迎えての例会となった。
豊後街道顕彰会に参加した会長が説明した。
 
◎今ひとたびのふるさと
嘉悦 渉 先生
詩歌 第七回 「園田太邑」
文部省により学制が頒布されたのは明治五年(一八七二年)。 翌六年には、宮地、坂梨、古城、中通の各村には小学校が創設されました。 その中でも中通小学校は明治四年阿蘇日新社として発足、寺子屋の域を脱し既に小学校教育の原型を整えていたといわれています。 この阿蘇日新社の創設に参画したのが園田太邑です。
太邑は嘉永七年(一八五四年)豆札に生まれ幼い時から学問を好み年を重ねるごとに才能をのばし、後に熊本に出て元田永孚、竹崎茶堂の教えを受けその高弟となりました。 和漢の学を究め晩年坂梨に帰り塾「倍達堂」を開き郷里の青少年の教育にあたりました。 多くの門人から外務大臣となった内田康哉、衆議院議員林田亀太郎、九州新聞(熊日の前身)社長高木第四郎などがうまれました。 太邑は俳句は「千里軒牛歩」、漢詩は「蘇門」と号し多くの秀句を残しています。 また、文筆家として書もよくし中通小学校創立五十年記念碑の碑文を稿し筆をふるっています。
昭和三年(一九二七年)十月二十二日没
辞世句
夜は疾く、明けたり壁のきりぎりす
大根引きし跡の畑や 霜の花
参考文献 一の宮町教育委員会 甲斐敏子(熊本市)所蔵
 
例会審議事項
●坂梨宿場ホッと一息ギャラリーの件
日程 十二月三日、四日(土、日)
会場 工芸滝室、石村家具店、なごみ野 の各店
時間 午前十時から午後五時まで
展示 従来の作品等に加えて、今回阿蘇市在住の工芸家四名による木工芸、鉄工芸、陶器、布織物を新たに参加頂き一層の鑑賞を楽しむ事が出来るようにしました。
●忘年会の件
日程 十二月四日(日)
会場 なごみ野
時間 午後七時から
会費 金弐千円
幹事 高木勘定方
準備の都合がありますので、出席希望者は事務局までご連絡下さい。 十二月三日まで
例会差入披露
阿部さん 清酒寒北斗 一升
古木会員 焼酎 一本
田上会員 焼酎 一本
志賀会員 カステラ巻 一箱
差し入れ有り難く頂戴しました。
今月の話題
常夜灯第四十四号設置
石田会員が制作した常夜灯が上町組江藤さん宅に、十一月十三日に設置され灯りが入りました。 石田会員は自宅用の常夜灯をこれまでより一回り大きく、色も変えて立派な物にするため新たに制作し最近設置したばかりでしたが精力的に制作を続けると共に、ご近所への設置を呼びかけなどの積極的な活動を展開しています。 上町組は灯りが点々と等間隔に増えて一層風情を醸しています。
 
十二月例會案内
十二月四日(日)午後七時 忘年会併催
特別会費 2000円
場所 なごみ野 於
|